第七回(最終回) 風の森(南大和の戦い)
正平三年(一三四八年)正月の「四条畷の戦い」に続く翌二月の、田中俊資(としすけ 南北朝戦史研究家)氏が名付けた「南大和の戦い」こそ、「太平記」から全く抜け落ちるが故に、知る人もなく、南北朝史から脱落する部分である。歴史の進行に平行して書き下ろされた大長編叙事詩に時の権力者が圧力をかけ、幕府が吉野方に敗北した唯一の戦いを意図的に削除させたのだろう。それとも田中俊資氏の夢想した創作物語なのだろうか。否、そうではない。如何に負けず嫌いの高師直(こうのもろなお 四十七歳)が、臆面もなく大敗した吉野攻めを大勝利と将軍家や世間に吹聴し、京に大見栄切って凱旋したとて、彼がこの戦で獲たものは何もなく、大半の部下を失ったからには、最早尊氏(たかうじ 四十三歳)直義(ただよし 四十一歳)共に、室町幕府を安定的に鼎立(ていりつ)させる三本柱の一つとして立てなくなったのは間違いない。だからこの直後、観応の擾乱(じょうらん)と世に言う、南朝を巻き込んでの「足利の内輪もめ」が勃発し、直義の指示によって弟師泰(もろやす 四十六歳)共に暗殺されたのだ。これは師直師泰が南朝に敗北したことに由来する結果である。
楠正行(まさつら)の戦死、南朝全軍を震撼させる
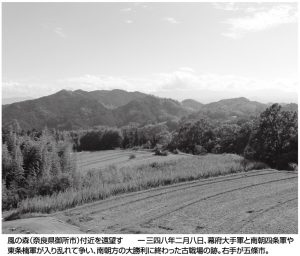 雲霞の如き大軍の攻撃を受け、味方の兵を際限なく失いながら、東高野街道を北に深く突き進んだ楠和田精鋭部隊が、幕府軍総大将、高師直が本陣を置く北条(四条畷駅付近)で全員討ち死にしたことは、光明池の北畠親房や和田正武にも、槙尾山の興良(おきなが)親王にも、東条(河南町)赤坂(千早赤阪村)の楠家留守部隊を率いる楠正儀(まさのり 楠家三男 二十歳)にも、無傷の南朝軍主力部隊六千の兵を率いて當麻(たいま)寺で正行たちの帰還を待つ四条隆資(たかすけ 五十五歳)にも、その日の内に伝わった。
雲霞の如き大軍の攻撃を受け、味方の兵を際限なく失いながら、東高野街道を北に深く突き進んだ楠和田精鋭部隊が、幕府軍総大将、高師直が本陣を置く北条(四条畷駅付近)で全員討ち死にしたことは、光明池の北畠親房や和田正武にも、槙尾山の興良(おきなが)親王にも、東条(河南町)赤坂(千早赤阪村)の楠家留守部隊を率いる楠正儀(まさのり 楠家三男 二十歳)にも、無傷の南朝軍主力部隊六千の兵を率いて當麻(たいま)寺で正行たちの帰還を待つ四条隆資(たかすけ 五十五歳)にも、その日の内に伝わった。
幕府軍を吉野渓谷に誘(おび)き寄せるには、楠軍の大敗が必要なことは共通認識だったが、彼らが全員還らぬ人となるとは、誰一人想像も覚悟もしてはいなかった。
軍師、北畠親房は正行の死を嘆く寸暇も無く、これで勢いづく敵の攻撃に備えるため、和田正武には和泉に戻って守りを固めるよう指示し、自身は急ぎ槙尾山に戻り、興良親王と合流すると周辺の守りを固め、東条・赤坂の楠正儀にも守りを厳重に固めるよう指示し、當麻寺の四条隆資軍には、下街道(国道二十四号線)を南下し、風の森を越えて宇智郡(五條市)に入り、予定通り吉野川の丹生(にう)川河口付近(五條市役所付近)で御所方面から押し寄せる敵に対し、鶴翼(かくよく)の陣を布(し)くよう命令書を送った。
吉野朝廷、穴生(あのう)への遷宮を決す
 四条隆資(たかすけ)には驚愕の事態だ。宇智郡で敵と戦うのは予定通りだが、指揮するのは戦場から撤収してくる楠正行だと勝手に想像していた。よもやこの自分が、主力部隊を指揮し、大軍で押し寄せる高師直と決戦するなどとは思ってもみなかった。主力軍とは兵の数だけ。紀伊や大和の郷士と言えば聞こえは良いが、野武士風情を寄せ集めたに過ぎない。隆資は震えが止まらなかった。
四条隆資(たかすけ)には驚愕の事態だ。宇智郡で敵と戦うのは予定通りだが、指揮するのは戦場から撤収してくる楠正行だと勝手に想像していた。よもやこの自分が、主力部隊を指揮し、大軍で押し寄せる高師直と決戦するなどとは思ってもみなかった。主力軍とは兵の数だけ。紀伊や大和の郷士と言えば聞こえは良いが、野武士風情を寄せ集めたに過ぎない。隆資は震えが止まらなかった。
吉野の後村上帝(二十歳)にも六日の昼には正行討死の報が届いた。正行が生還する暁には、彼との祝言を夢見られていた弁内侍(べんのないし 二十二歳)様だが、悲報を聞くなり部屋に一人閉じ籠もってしまわれた。後刻、気がつけば内侍は髪を下ろされていた。
翌日、洞院実世(とういんさねよ 四十歳)を進行役に御前会議が開かれ、このような事態も予想し、予め定められていた方針が再確認された。即ち来る十四日、帝をはじめ、総ての公家女官らは、御所や住居を捨て、南の穴生(あのう 賀名生)に移住することとなった。しかし幕府側に見咎められぬよう、伊勢街道は通らず、西南に険しい山道を下って黒滝村を抜け、丹生川の源流から川を下って、城戸から穴生に入ることとなった。しかし万が一敵に穴生が襲われる場合も考え、帝は若干の近習を連れ、城戸で皆と別れて更に奥地へと進まれ、乗鞍岳西尾根を越え、十津川花園村(十津川村風屋ダム付近)に身を隠されることになった。
高師直、師泰に吉野朝廷掃討の命が下る
後村上帝は伊勢の北畠顕能(あきよし 親房の次男 二十八歳)に出陣を命じられ、南大和、吉野、熊野、紀伊の勤皇の諸勢力にも加勢を命じられた。
将軍から東条攻めを命じられた高師泰は、八千騎の兵を率いて堺を出発し、竹内街道を東進し、八日夕刻には石川の河原に到着する。周辺の寺社に兵糧の供出を命じるも拒否されると、怒りに任せて寺社を放火して回った。彼らの狼藉は五日間も続く。京には神仏を恐れぬ師泰が聖徳太子聖廟を焼失させたと伝わり、世評が気になる将軍家を困惑させた。
幕府軍総大将、高師直は十五日、一万八千騎の兵を引いて八尾教興寺から国分を経て長尾街道を東進し、當麻寺に到着した。そこに尊氏からの急使が着く。吉野とは和議を結ぶべく交渉中であって、別命あるまで吉野川は渡河せぬよう、と師泰同様、聖域でも神仏を怖れず狼藉しかねない師直軍を牽制するものだった。
十四日、師泰軍は東条に入ったが、抵抗する楠兵は一人もおらず、腹いせに楠館や農家を焼き払った。師泰は高笑いした。「正行なき楠勢とはこんなもの。儂らに畏れをなし、領地を捨てて逃げ去ったか。」師泰は戦勝の証しに、東条、赤坂に分散して駐屯を続けるしかなかった。しかしその夜から楠正儀、楠正茂(まさもち 三十三歳)らによる夜襲を受け、師泰軍はおちおち安眠もならず、やがて石川の河原まで撤退するしかなかった。
吉野山炎上す
 南朝の公達たちは十九日、穴生(賀名生)に到着。何故遷宮の先として、かくも深山幽谷の地が選ばれたか。それは京から吉野への先帝御動座を仲立ちし、ご援助申し上げたのが穴生の掘家であり、今回も掘家を頼ってのことだった。自宅を皇居として提供申し上げたのも掘家である。(この皇居跡、現在も賀名生に保存され、付近には十年前から駐車場が整備され、歴史民俗資料館が建つ。)
南朝の公達たちは十九日、穴生(賀名生)に到着。何故遷宮の先として、かくも深山幽谷の地が選ばれたか。それは京から吉野への先帝御動座を仲立ちし、ご援助申し上げたのが穴生の掘家であり、今回も掘家を頼ってのことだった。自宅を皇居として提供申し上げたのも掘家である。(この皇居跡、現在も賀名生に保存され、付近には十年前から駐車場が整備され、歴史民俗資料館が建つ。)
二十五日、師直は飛鳥(あすか)橘寺に全軍を集結させ、四条軍が吉野川の丹生川河口に布陣することを確認した。翌二十六日、佐々木道誉(どうよ)軍には南西方向に進軍させ、古瀬(巨勢)の辺りで駐屯し、重阪(へいさか)峠を挟んで四条軍前哨部隊と対峙するよう命じた。又武田氏信には中街道を下市に向かわせ、伊勢街道阿田付近で待機するよう命じ、自らは本隊を率いて高取山壺坂峠を越え、上市の吉野川北岸に布陣する。
渡河を禁ずる将軍の命を懸念する将らの前で「何が霊験あらたかな聖域じゃ。構わず兵を入れて蹂躙(じゅうりん)し、小賢しい公家共を脅しつけるのじゃ。でないと和議など進まぬぞ、」と嘯(うそぶ)き、二十八日、全軍に渡河を命じ、そのまま吉野山まで一気に押し寄せた。
山上には南朝に仕える公家など一人もおらず、寺社関係者も逃げ去った後だった。「穴生動座の噂はまことだったか」と、兵たちの苦難の雪中登山を徒労に終わらせた師直は腹立ち紛れに、目前の寺社や皇居を焼き払うように命じた。
太平記は、この時、吉野山の堂搭伽藍(がらん)が灰燼(かいじん)に帰したとするが、それは師直を極度に悪人にしたくての誇張であろう。無論今日まで吉野の堂搭も何度か建て直しがあったに違いない。しかし全山が灰燼に帰すほどならば、吉野朝廷時代の雰囲気を残しての今日の様な歴史的景観の保存は不可能だったと思うからだ。
幕府軍、水越峠を占領し、先手を打つ
炎上する吉野山を後にし、師直は、細川頼春率いる二千の兵に吉野川左岸を進むよう命じた。本隊には再び渡河を命じて、伊勢街道を上市から下市へと軍を進め、二千の武田軍と再び合流して四条軍の様子を伺った。
膠着状態のまま二月に入った。その頃、弟師泰が楠軍によって東条赤坂から撃退され、石川の河原まで退いたことが師直にも伝わった。
(東条の楠軍が健在なることは、我ら大手軍にも由々しきこと。東条赤坂の後ろに聳えるのは葛城、金剛だが、楠領から両山を結ぶ水越峠を越えるなら、目前の盆地が古瀬であり、右手の丘陵が風の森なのだ。師泰軍が攻撃の手を弛めれば楠軍は峠を越えるであろう。我らが宇智郡の四条軍と決戦になれば、峠を越えた楠軍が背後に回り、我らを挟み撃ちにすることは誰にも予想できることだ。)
師直は、古瀬に駐屯する三千の佐々木軍に、水越峠に一部兵を回すよう命令した。五百の兵を率いて水越峠の占領に向かったのは、佐々木道誉の次男、秀宗だ。秀宗は峠の周囲に柵を二重三重に打ち込み、峠そのものを砦として、猫の子一匹通さぬようにした。
またこの頃、飛鳥の奥の多武峰(とうのみね)に、僧の西阿が長谷寺や談山神社の僧兵衆徒を何百と集め、蜂起しようとしているとの情報がもたらされた。
(興国年間に南朝に与し、蜂起した開住の西阿は生きていたのか。そう言えば高野街道讃良(ささら)の戦い(四条畷の戦い)で正行を慕って参戦し、討ち死にした良円は西阿の息子だったと聞く。良円の怨念が親の西阿を生き返らせたか。これはやっかいな。)
宇智郡での決戦が二月八日に決まる
 師直は考えた。(恐らくこういう輩は、伊勢からやって来る北畠顕能軍と合流するつもりなのじゃ。では北畠は何時この南大和に顔を見せるのじゃ。)
師直は考えた。(恐らくこういう輩は、伊勢からやって来る北畠顕能軍と合流するつもりなのじゃ。では北畠は何時この南大和に顔を見せるのじゃ。)
伊勢に放った斥候の報告では、北畠顕能(あきよし 顕家の弟)は千五百騎を集め、出陣を急いではいるが、準備に手間取り、出立は今日明日のことではなさそうだ。早くても大和の三輪に到着するのは、二月八日か九日であろうと。それを聞いて師直、腹を決めた。来る六日に和泉和田を攻撃し、七日には東条を総攻撃しろ、との命令書を石川の河原にいる弟師泰に送り、幕府軍本隊と南朝主力部隊との決戦の日を二月八日と決めた。
(北畠顕能よ、貴様が三輪山麓に到着する頃には、宇智郡の四条隆資も、東条の楠正儀も、和泉の和田正武も、ことごとくこの地上から消えているだろうよ。)
四条隆資(たかすけ)は吉野川の側に陣を構えながら、これまでの思慮の浅さを反省するのだった。人の情も捨て、鬼神となった軍師親房の戦略が、敵の囮(おとり)となって味方の次の勝利に生命を捧げた正行の心が、しっかりと理解できるようになった。
(次に命を捧げるのは、この私だ。敵をこのような渓谷に誘き寄せたのは、沢沿いの長くて細い坂道では、どんな大軍が押し寄せようが、一列縦隊で進まねばならないからだ。それを両側の丘陵から弓矢で挟撃することで、小が大を殲滅する作戦だった。ところが従う兵らは指揮官の臆病な顔色を伺ったか、多数が離散し、今や四千しか残っていない。これでは左右の丘陵に伏兵を割く余裕もない。敵の右翼、佐々木軍は下街道を目前に迫り、師直軍本隊も伊勢街道からこちらに進軍している。左翼細川軍は吉野川左岸をこちらに向かって進軍しているようだ。このままでは挟撃されるは敵でなく、我が軍だ。)
宇智郡にも、東条にも、思わぬ援軍が到着
四条隆資は死を覚悟した。ふと昔、鎌倉幕府転覆を謀った天皇後醍醐の身代わりとなり、進んで斬首の刑を受けた日野俊基(としもと 正行許婚者弁内侍の父、正成を勤皇の武士に変えた思想家)の辞世の詩を思い出した。
(「古来一句あり、死も無く生もなし、万里の雲尽きれば、長江の水清し」 そうだ。誰にも死は訪れる。連戦連勝の英雄も何時かは必ず滅びの死が訪れるのだ。しかし人間とは何だ。滅びる肉体が人間の本性であるはずがない。国を想い民族を愛する魂は滅びないぞ。だから人には勝つことよりも大切なことがある。私たちはこの国をどうしたかったのじゃ。太陽の神、天照大御神は、尊き子孫の皇子様方に、この瑞穂の国を永遠に統治させると宣言されたのだ。それがこの国の誕生以来曲げられぬ大法なのだ。大御神様、どうかこの大法に捧げる私たち四千名の命を、御心のままにお使い下さい。)
隆資は全軍を集め、この果てしない戦いの目的と、自らの覚悟を懇々と説いた。その時だった。陣中から、そして宇智郡の渓谷全体から轟き渡る歓声が起こった。
紀州の楠木縁者、牲川(にえがわ)、貴志、生地の三氏が、合わせて千五百名の兵士を連れ、また熊野の勤皇の郷士たち五百名も、同時に四条軍に味方する為に今到着したのだ。これで四条隆資は再び六千名の兵を率いることになった。
到着した二千の楠縁者や熊野の勇敢な郷士たちは、宇智郡に押し寄せる敵の中で、最も攻撃的に突出する右翼の佐々木軍を抑えようと、自発的に自分たちは左翼に布陣することを希望した。(奈良カントリークラブ辺りか)
二月六日、和泉和田を攻めようとした幕府軍は春木谷で和田正武軍の待ち伏せに遭い、多数の兵を失って退却した。翌七日、東条に総攻撃をかけた師泰だったが、紀州から安間余一らの援軍を得ていた楠軍の激しい抵抗を受け、これも退却してしまった。
二月七日の陽が暮れると、多武峰から進軍してきた開住西阿の七百名の兵が、古瀬西側の丘陵の森に密かに身を隠した。(秋津原ゴルフクラブの辺りか。)
楠軍、水越峠の柵を突破し、南大和に侵入する
八日夜明け前、水越峠を守備する佐々木秀宗は、峠の周囲三方向の山の木々が激しく焼ける明るさと物音に驚き飛び起きた。「敵襲だ!」既に数名の兵達は全身火達磨になって、狂ったように走り回っている。佐々木軍は本能的に炎の見えない山の西側に下ろうとした。そこには楠勢が弓矢を構えて待っている。実戦経験に乏しい若い司令官に率いられた可哀想な兵達は、火傷で動けなくなるか、矢傷で動けなくなるかして、一瞬の内に全滅した。
火が収まって黒こげになった柵を壊すと、楠軍は一斉に水越峠を越え、一言主神社に下って夜が明けるのを待った。霧の立ちこめる中、空が明るくなると四条軍への合流を急ごうと古瀬の盆地には降りずに、金剛東山麓をそのまま風の森の高鴨神社へと急いだ。
朝靄の中、宇智郡の吉野川にも八日の朝が明けた。天候は曇り空。四条軍に最も接近しているのは、幕府軍右翼の佐々木道誉。だが眼前に菊水の旗を掲げ、紀州から楠の縁者が加勢に来ているのを見てぎょっとなった。(しまった、お人好しにも深入りしすぎた。腹黒い師直のこと、敵左翼が楠縁者だと知って、この儂(わし)を右翼に配置させたのか。敵を破っても良い、儂が敗れても良い、という作戦に違いない。よし、師直が四条軍とぶつかる時刻まで、風の森に後退し、見物するとしよう。)佐々木軍は風の森への元来た坂道を登って後退し始めた。
そこへ水越峠が楠軍に襲われたとの報が伝わる。(なんてことだ。秀宗を死なせてはならぬ。)息子の生死を案じて動転した佐々木道誉は、四条軍と戦うことも忘れ、戦場から離脱し、風の森を抜け、金剛東山麓を水越峠に急ごうとした。しかし風の森の出口の先には、楠正儀、安間余一らが道の側面に隊列なして弓矢を構えるのを知る由も無かった。
幕府軍は自ら崩壊し、南都に総退却する
伊勢街道と下街道の合流点まで兵を進めた師直だったが、目の前で佐々木軍が後退するのを見て驚いた。息子の安否が気がかりだとは言わず、東条の楠軍が水越峠を越え、我らの背後に回ったのを抑えに行くのだと佐々木軍は尤もらしい言い訳をした。
そういう時の為、遊軍として後陣に控えさせていた細川顕氏(あきうじ)二千の兵に、前進して右翼に付け、と命じようとしたが、どうしたことか顕氏の兵は後ろにいなかった。聞くと、三輪山方面に北畠軍が現れたので、それを抑えに行って来る、と離脱したとのこと。(そういうことなら、顕氏に多武峰に開住西阿ら数百名が集結していることを教えておくべきだった。)実は、顕氏は楠の間者(かんじゃ)が流した偽りの情報に騙され、持ち場を離れてしまったのだ。北畠軍はまだ長谷寺にも到着していなかった。
後退した佐々木軍を追って、牲川、貴志、生地らの精鋭部隊が下街道を登って来る。四条軍も後に続いて進軍を開始した。師直は、この場は武田軍に任せようと、本隊に後退を命じた。本隊の後退を対岸で見ていた細川頼春は、何か重大な作戦の変更があったと、慌てて自軍に上市まで後退するよう命じたのだ。戦場は大混乱となった。師直は総退却を命じたつもりはなかったのだ。ただ武田軍の後ろに回ろうとしただけだった。
幕府軍の全兵士が風の森や重阪(へいさか)峠を越えて恐怖に怯えるように我先に退却を始めてしまった。仕方なく師直は身の危険を感じて親衛隊を率いて古瀬の西の深い森の中に一時身を隠すことにした。けれどもまだ師直は戦況を楽観していた。兵たちもその内戻ってくるだろうと。しかしその森には西阿率いる七百名ものゲリラ兵が、獲物を待ち構えていることなど知る由も無かった。
エピローグ
連戦連勝の将だった高師直も、佐々木道誉も、この南大和の戦いでは、ふとした疑心暗鬼が元で事態が悪く、悪く循環する内に大敗してしまった。両将共、それぞれ大混戦の中で部下の兵達に「生きて逃げおせ、南都で遭おうぞ」と大声をかけ、南都(奈良町)に命からがら逃げ帰って兵達の還りを待ったが、殆どの兵は戻らなかった。
この後、高師直は失脚し、直義の命で暗殺された。すると次は尊氏と直義との争いとなるのだが、それは直義が尊氏に毒殺されるまで続くのである。
しかし室町幕府の統治システムを創ったのは直義であって尊氏ではない。直義は悪人と後世に伝えられるが、実に優れた政治家だった。一方尊氏は戦上手の他は見るものがない。直義の優れた政治手腕は、皮肉にも政敵の足利義詮(よしあきら 尊氏嫡男)に引き継がれた。義詮も直義同様、戦は苦手だ。しかも義詮は父尊氏が生存の間、常に父の陰にいて目立たなかった。だが南北朝の内乱の収拾には並々ならぬ働きをした。義詮が果たし得なかった事業を成したのは、その子の義光である。名高い英雄を父に持つ二代目同士、親近感を感じていたのか、嵯峨野宝筐院にある楠正行首塚の横に自らの墓を建てよ、と義詮は遺言した。今、二人の墓は仲良く庭園の奥に並んでいる。
賀名生の後村上帝はさぞや京に戻りたかっただろう。一時的には観応の擾乱に紛れて京を占拠されたこともある。その時、「夢叶う」と穴生の表記を帝は賀名生と改められた。
その後も南朝が京に戻れる機会は何度もあった。足利幕府にすれば、幕政さえ認められるのなら京の天子は北朝でも南朝でも良かったのだ。しかし京に戻れる機会を悉く壊してきたのは、頑迷な程に、成らぬものは成らぬと、武家方との妥協を嫌った北畠親房だ。彼の墓(円墳)は賀名生の御所を見下ろす岡の上にある。親房は吉野の山から、世界に日本を貶(おとし)めて廻る隣国二国にはっきりものが言えない今日の日本政府をどのように見ているだろうか。
長い間、このシリーズをお読みいただいた皆様に感謝申し上げます。またこのシリーズ第二部を書くに当たって、貴重な資料を残して下さった故田中俊資氏には低頭して感謝の念を捧げます。